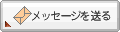2021年09月23日
レーザー彫刻機を買った!
春頃に小型のレーザー彫刻機のクラウドファンディングが始まったのをたまたま見つけました。
Runmecy(ランメシー)という機種なんですが、超小型で高出力、そしてお手頃な値段との事で、思わず購入した物が先日ようやく届きました。

ボディはえらく小さいです。
出力は5000mW。
こういう事には明るくないんですが、このクラスの小型機は1600mW~3000mWが主流で、5000mWは破格の高出力らしいです。金属にも刻印できちゃいます。

さっそく、ABS板にテストしてみました。

かなり小さい文字もきちんと刻印できました。
しかし、加工中は樹脂が焦げる臭いで気持ち悪くなります。きちんと換気するか、次はベランダでやろうかな。小型機だからそんな事もできます。
ちなみに、最初はよく分からずに高出力で刻印したら、2mmのABS板を貫通してしまいました。カットにも使えそうだと実感。
金属にも彫刻可能という事でステンレス板でも実験。

できましたが、周りが焦げました。
しかし、コンパウンドで磨けば問題なし。

ステンレスには可能ですが、アルミは不可です。反射率の問題だとか。
こういうアイテムは初めてなので、しばらく遊べそう。
カスタムガンを作る際にも活躍してくれそうです。
しかし、自分がレーザー彫刻機を買う日が来るなんて想像もしなかったなぁ。
Runmecy(ランメシー)という機種なんですが、超小型で高出力、そしてお手頃な値段との事で、思わず購入した物が先日ようやく届きました。

ボディはえらく小さいです。
出力は5000mW。
こういう事には明るくないんですが、このクラスの小型機は1600mW~3000mWが主流で、5000mWは破格の高出力らしいです。金属にも刻印できちゃいます。

さっそく、ABS板にテストしてみました。

かなり小さい文字もきちんと刻印できました。
しかし、加工中は樹脂が焦げる臭いで気持ち悪くなります。きちんと換気するか、次はベランダでやろうかな。小型機だからそんな事もできます。
ちなみに、最初はよく分からずに高出力で刻印したら、2mmのABS板を貫通してしまいました。カットにも使えそうだと実感。
金属にも彫刻可能という事でステンレス板でも実験。

できましたが、周りが焦げました。
しかし、コンパウンドで磨けば問題なし。

ステンレスには可能ですが、アルミは不可です。反射率の問題だとか。
こういうアイテムは初めてなので、しばらく遊べそう。
カスタムガンを作る際にも活躍してくれそうです。
しかし、自分がレーザー彫刻機を買う日が来るなんて想像もしなかったなぁ。
2021年09月16日
リニューアル!ガバメントシリーズ(マルシン)組み立てキット

マルシンのガバメントシリーズ(M1911A1、シリーズ'70、コマンダー)がリニューアルして再販されました。
まずは組み立てキットから発売、完成品は1週間ぐらい遅れて出荷されるようです。
これまでの再販でもマイナーチェンジされる事はありましたが、今回は結構本格的なアップデートです。特にM1911A1。
というわけで、私はM1911A1を購入しました。
まだ組み立てていませんが、改良された部分を中心に見ていきます。

マルシンのミリガバが、どうしてもミリガバっぽくなかった部分。スライドストップとメインスプリングハウジングがチェッカリングになりました。ハウジングの内側は、従来のマルシンガバと同じ「片側だけ」仕様です。

グリップパネル。これもフルチェッカーにネジ穴周りの台座があるお馴染みのミリガバ仕様になりました。グリップの見た目は最も銃の印象を左右しますので、これのお陰で圧倒的に「ミリガバ」っぽい見た目になっています。
またグリップ裏にはみっちりウェイトが仕込まれているので、他社ガバに流用してウェイトアップなんて使い方もできそうです。

形状が変更されたフロントサイト。
グルーブなしです。ちょっと幅が広い気がするのですが、この辺のマニアックな部分は私は正解が分かりません。

インナーシャーシが金属になってます!!!
マルシンガバのシャーシは、古くは金属でしたが、いつからか樹脂になり(タニコバコラボのMTでは金属でしたが)、そのせいで持った時のスカスカ感が萎えポイントでした。
これで重量がかなりアップすると同時に、剛性感も増しました。
以前のモデルは実物グリップを装着しようとするとプランジャーチューブが当たってしまい、加工が必要だったのですが、今回はプランジャーチューブの形状が変更されているようです。これで実グリもすんなり付くでしょう。ちなみにフレームのグリップ部分がやや短いのはそのままです。
またシャーシのフィードランプ部分の形状が変更されています。給弾性能向上のためだと思われます。

刻印は変わりないようです。
ダストカバーも今まで通りです。
今回、アップデートポイントが多かったのはこのミリガバで、だから私はコレを買ったのですが、シリーズ'70やコマンダーもメインスプリングハウジングの底部形状や、グリップの仕様などが変更されており、当然シャーシも金属になっているはずです。
これでマルシンガバに対する不満はかなり減りました。
キットだと市場価格は1万円台中盤ですから、おウチ時間のお供に1挺おすすめです。

ハイパワーに続き、『俺のガバメント フォトコンテスト』も開催されます。
今回再販されたキットを組み、写真を撮って応募すれば、全員必ず参加賞としてマルシンステッカーがもらえます。そして優秀作品には金のガバや銀のガバなどの激レアアイテムも贈呈されます。
応募は郵送、Eメールの場合は2021年11月22日まで。
Twitterの場合は2021年11月22日〜28日の間に「#俺のガバメント」のハッシュタグをつけて投稿。
今回は2ヶ月ぐらい製作期間があるので、ぜひ参加しましょう!
2021年09月10日
改造モデルガンで老ユーチューバー逮捕の件
6月に改造ハイパトで逮捕の件を書いたばかりですが、3ヶ月足らずでまた逮捕者が出たので残念ながら再度このような記事を書きます。
事件のあらましとしては、
愛知県に住む70歳男性が、モデルガンを改造した拳銃8挺と、色を塗り替えた模造拳銃2挺を所持していたとして、警視庁に逮捕された。
というものです。
この男性が公開していた動画に関しては、少し前にネット上のマニアをざわつかせたので、ご記憶の方もいらっしゃると思います。
私が見たのは、龍馬の銃のモデルガンのバレル及びシリンダーのインサートを除去し、それを撮影した動画を誇示するように公開していたものです。
ハイパト事件の時も書きましたが、もう一度明確に記しておきます。
模造拳銃や模擬銃器は金属で作られている事が要件なので、樹脂製モデルガンにインサートがあるのは自主規制であって、樹脂製モデルガンのインサートを除去しても違法ではない…
…という解釈をしている人がいれば、それは大間違いです!
撃針から銃口まで一直線に筒抜けになっていれば、弾丸を発射できる構造なので、それは模造拳銃を通り越して「真正銃」です。素材が何であろうが逮捕されます。
しかも本件の被疑者が悪質だったのは、後撃針で発火でき、なおかつ先端に弾を詰められるようなカートリッジまで自作していたと見られる事です(動画では詳細に説明せず「匂わせ」だけでしたが)。
これはもう、完全に武器を製造していますから、情状酌量の余地はありません。
念のために書きますが、今回例に挙げた龍馬の銃は、自主規制組合STGAの厳格な基準のもとで製造・販売されていますから、「改造する事はほぼ不可能」と言ってよく、危険性はゼロに近いです。当然、販売したメーカーに落ち度はありません。
被疑者が異常な執念と特殊な技術で改造したと考えられます(弾薬を自作しているあたりからして異常)。
さらに金属製モデルガンを白、黄色以外の色に塗り替えた模造拳銃も押収されていますが、被疑者の年齢と経歴からすると、モデルガンの法規制やその経緯を知らなかったとは考えられず、こちらも悪質と言わざるを得ません。
モデルガンは恐ろしく厳しい法規制、さらにそれを上回る組合の自主規制を、メーカーの工夫と不断の努力によりクリアして存在できています。
これはユーザー1人の不届きな行為によって崩壊するような微妙なバランスで成り立っていますから、「自分1人ぐらい悪さしちゃっても大丈夫だろう」という考えの人がいれば、今すぐその思考を改めて頂きたい。「誰にも見せずに自宅にしまっておけば大丈夫」というのは幻想です。必ず逮捕されます。
「法律がおかしい」と感じてそれが我慢できないのであれば、自分が政治家になって法律を変えるか、法律を変えてくれそうな人に投票してください。自分が「おかしい」と感じただけで違法行為に及ぶのは、テロに等しいです。
ちなみに、私も主催者のひとりである『モデルガンカーニバル東京』は、モデルガンを発火して遊ぶイベントであると同時に、法律遵守の啓発イベントでもあります。イベントではほぼ毎回、STGAの小林太三技術部長に銃刀法に関する講義を行って頂いています。しかし社会情勢によってここ2年ほどイベントが開催できていないので、何らかの形でまた小林社長にお話し頂ける機会を作りたいものです。
それにしても、メーカーの努力によって外観や性能に何の不満もないモデルガンが入手でき、弾を飛ばしたければエアガンをいくらでもチョイスできる時代で、このような犯罪に手を染める人がいるのは何なんでしょうか?
私はずっとその事が疑問です。どのような思考回路なのか知りたいです。
もし被疑者と同じような願望を持っている、あるいは同様の罪を犯して逮捕された事があるという方とコンタクトがとれるなら、ぜひ話を聞いてみたいです。一体何が望みなのか?
ちなみに、「前方からの見た目に不満がある」という事であれば、このようなアクセサリーも販売されています。

C-Tec製ダミーブレット。
シリンダーインサートに挟み込むように取り付ける飾りで、おまけに銃口をふさぐ黒い樹脂製のフタも付属していますのでディスプレイに最適です。前からの眺めを良くしたい方はぜひご検討ください。

事件のあらましとしては、
愛知県に住む70歳男性が、モデルガンを改造した拳銃8挺と、色を塗り替えた模造拳銃2挺を所持していたとして、警視庁に逮捕された。
というものです。
この男性が公開していた動画に関しては、少し前にネット上のマニアをざわつかせたので、ご記憶の方もいらっしゃると思います。
私が見たのは、龍馬の銃のモデルガンのバレル及びシリンダーのインサートを除去し、それを撮影した動画を誇示するように公開していたものです。
ハイパト事件の時も書きましたが、もう一度明確に記しておきます。
模造拳銃や模擬銃器は金属で作られている事が要件なので、樹脂製モデルガンにインサートがあるのは自主規制であって、樹脂製モデルガンのインサートを除去しても違法ではない…
…という解釈をしている人がいれば、それは大間違いです!
撃針から銃口まで一直線に筒抜けになっていれば、弾丸を発射できる構造なので、それは模造拳銃を通り越して「真正銃」です。素材が何であろうが逮捕されます。
しかも本件の被疑者が悪質だったのは、後撃針で発火でき、なおかつ先端に弾を詰められるようなカートリッジまで自作していたと見られる事です(動画では詳細に説明せず「匂わせ」だけでしたが)。
これはもう、完全に武器を製造していますから、情状酌量の余地はありません。
念のために書きますが、今回例に挙げた龍馬の銃は、自主規制組合STGAの厳格な基準のもとで製造・販売されていますから、「改造する事はほぼ不可能」と言ってよく、危険性はゼロに近いです。当然、販売したメーカーに落ち度はありません。
被疑者が異常な執念と特殊な技術で改造したと考えられます(弾薬を自作しているあたりからして異常)。
さらに金属製モデルガンを白、黄色以外の色に塗り替えた模造拳銃も押収されていますが、被疑者の年齢と経歴からすると、モデルガンの法規制やその経緯を知らなかったとは考えられず、こちらも悪質と言わざるを得ません。
モデルガンは恐ろしく厳しい法規制、さらにそれを上回る組合の自主規制を、メーカーの工夫と不断の努力によりクリアして存在できています。
これはユーザー1人の不届きな行為によって崩壊するような微妙なバランスで成り立っていますから、「自分1人ぐらい悪さしちゃっても大丈夫だろう」という考えの人がいれば、今すぐその思考を改めて頂きたい。「誰にも見せずに自宅にしまっておけば大丈夫」というのは幻想です。必ず逮捕されます。
「法律がおかしい」と感じてそれが我慢できないのであれば、自分が政治家になって法律を変えるか、法律を変えてくれそうな人に投票してください。自分が「おかしい」と感じただけで違法行為に及ぶのは、テロに等しいです。
ちなみに、私も主催者のひとりである『モデルガンカーニバル東京』は、モデルガンを発火して遊ぶイベントであると同時に、法律遵守の啓発イベントでもあります。イベントではほぼ毎回、STGAの小林太三技術部長に銃刀法に関する講義を行って頂いています。しかし社会情勢によってここ2年ほどイベントが開催できていないので、何らかの形でまた小林社長にお話し頂ける機会を作りたいものです。
それにしても、メーカーの努力によって外観や性能に何の不満もないモデルガンが入手でき、弾を飛ばしたければエアガンをいくらでもチョイスできる時代で、このような犯罪に手を染める人がいるのは何なんでしょうか?
私はずっとその事が疑問です。どのような思考回路なのか知りたいです。
もし被疑者と同じような願望を持っている、あるいは同様の罪を犯して逮捕された事があるという方とコンタクトがとれるなら、ぜひ話を聞いてみたいです。一体何が望みなのか?
ちなみに、「前方からの見た目に不満がある」という事であれば、このようなアクセサリーも販売されています。

C-Tec製ダミーブレット。
シリンダーインサートに挟み込むように取り付ける飾りで、おまけに銃口をふさぐ黒い樹脂製のフタも付属していますのでディスプレイに最適です。前からの眺めを良くしたい方はぜひご検討ください。

2021年09月04日
USPの構造
先日、USPのフレーム交換に伴い、初めてフレームをほぼ完全分解した話を書きました。
その際にUSPの構造の特徴や設計方針などを再認識できたので、所感を書いておきたいと思います。ホントは分解記事の中で書こうと思ったのですが、長くなりそうだったので…。
以前、スクラッチビルド大会で活躍されているキノハナさんとUSP談義をしていた時、「USPのモデルガンを持っているなら、完全分解してみたほうがいい!」と強くすすめられました。キノハナさんは銃の構造に精通するメカマニアです。
対して自分は発火して遊べればそれでいいというテキトー人間なので(笑)、せっかくのアドバイスを頭の片隅におきつつも、分解してみる事はありませんでした。なんせUSPは分解/組み立てが面倒くさくて有名な銃です。
今回、フレーム破損によって背に腹は替えられなくなり、とうとう分解に至ったわけですが、さほどメカに興味のない自分でも、感じるものがありました。

銃を完全にバラしてみると、キノハナさんが力説していた話を思い出します。
「USPは1つのパーツが1つの役割しか担っていない」
例えばグロックの場合、トリガーバーがストライカーをコックしたり、AFPBを押し上げる役割も担っています。
ベレッタのトリガーバーは、ディスコネクターも兼ねています。
しかしUSPのトリガーバーはトリガーとシアーを繋ぐだけ。そしてシアーやディスコネクターなど、あらゆるパーツが独立して存在しています。
そのぶんパーツ点数は多くなるわけですが、考えようによってはシンプルな設計とも言えます。
USPは、それまで独創的な銃を輩出してきたH&K社が、オーソドックスな銃へと路線変更した事で知られています。
そしてこの事が語られる時、例として決まって挙げられるのは、「外装ハンマー式のDA/SAオート」「ブローニングタイプのショートリコイル」「1911に寄せた操作感」などです。
もちろんこれらはその通りなのですが、さらにプラス要素として、「内部構造も奇をてらっていない」と感じます。
一般的に、銃はパーツ数が少ないほど故障や作動不良が起きにくいと言われています。
しかしUSPは逆にパーツ数を増やし、1パーツ1機能に限定する事で作動不良を起こしにくくしているように思えます。万が一故障しても原因を特定しやすく、そのパーツだけを交換すれば良いわけだから、メンテナンス性も優れています。この辺りは設計思想の違いかと思います。
そのパーツ交換にしても、USPは完全分解する事なく、ほとんどすべてのパーツにアクセスする事ができます(だからこそ幾度もパーツ交換をしていながら、完全分解する機会がなかったわけですが)。
USPの構造は完成の域に達しており、だからこそH&K社は改良する事なく現行製品としてUSPを販売し続けているし、後継機であるP2000やP30、HK45も、基本的にUSPの設計がそのまま踏襲されています。1911のようなマスターピースにはなっていませんが、もっと評価されるべき銃だと思います。
USPのモデルガンをお持ちの方は、ぜひ一度完全分解してみる事をおすすめします!(とかずっと分解しなかったヤツが言う(^^;;;)。
その際にUSPの構造の特徴や設計方針などを再認識できたので、所感を書いておきたいと思います。ホントは分解記事の中で書こうと思ったのですが、長くなりそうだったので…。
以前、スクラッチビルド大会で活躍されているキノハナさんとUSP談義をしていた時、「USPのモデルガンを持っているなら、完全分解してみたほうがいい!」と強くすすめられました。キノハナさんは銃の構造に精通するメカマニアです。
対して自分は発火して遊べればそれでいいというテキトー人間なので(笑)、せっかくのアドバイスを頭の片隅におきつつも、分解してみる事はありませんでした。なんせUSPは分解/組み立てが面倒くさくて有名な銃です。
今回、フレーム破損によって背に腹は替えられなくなり、とうとう分解に至ったわけですが、さほどメカに興味のない自分でも、感じるものがありました。

銃を完全にバラしてみると、キノハナさんが力説していた話を思い出します。
「USPは1つのパーツが1つの役割しか担っていない」
例えばグロックの場合、トリガーバーがストライカーをコックしたり、AFPBを押し上げる役割も担っています。
ベレッタのトリガーバーは、ディスコネクターも兼ねています。
しかしUSPのトリガーバーはトリガーとシアーを繋ぐだけ。そしてシアーやディスコネクターなど、あらゆるパーツが独立して存在しています。
そのぶんパーツ点数は多くなるわけですが、考えようによってはシンプルな設計とも言えます。
USPは、それまで独創的な銃を輩出してきたH&K社が、オーソドックスな銃へと路線変更した事で知られています。
そしてこの事が語られる時、例として決まって挙げられるのは、「外装ハンマー式のDA/SAオート」「ブローニングタイプのショートリコイル」「1911に寄せた操作感」などです。
もちろんこれらはその通りなのですが、さらにプラス要素として、「内部構造も奇をてらっていない」と感じます。
一般的に、銃はパーツ数が少ないほど故障や作動不良が起きにくいと言われています。
しかしUSPは逆にパーツ数を増やし、1パーツ1機能に限定する事で作動不良を起こしにくくしているように思えます。万が一故障しても原因を特定しやすく、そのパーツだけを交換すれば良いわけだから、メンテナンス性も優れています。この辺りは設計思想の違いかと思います。
そのパーツ交換にしても、USPは完全分解する事なく、ほとんどすべてのパーツにアクセスする事ができます(だからこそ幾度もパーツ交換をしていながら、完全分解する機会がなかったわけですが)。
USPの構造は完成の域に達しており、だからこそH&K社は改良する事なく現行製品としてUSPを販売し続けているし、後継機であるP2000やP30、HK45も、基本的にUSPの設計がそのまま踏襲されています。1911のようなマスターピースにはなっていませんが、もっと評価されるべき銃だと思います。
USPのモデルガンをお持ちの方は、ぜひ一度完全分解してみる事をおすすめします!(とかずっと分解しなかったヤツが言う(^^;;;)。