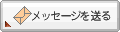2019年08月29日
コマンダーとハードボーラーが出る!
タニオ・コバのGM-7/7.5をベースとしたカスタム製品が、立て続けに発表されています。
どちも個人的に注目の製品です。
まずはおなじみ、BWCから、
ハードボーラーです。

(画像はMGC製)
いわゆるターミネーターの銃です。
これまでGM-7で6インチモデルはカスタム製品として発売された事がありますが、7インチモデルは初めてです(たぶん)。
スライドは新規金型で製作され、ワイドトリガーなどの特徴的なパーツもロストワックスや削り出しで作られるとの事。
7インチガバって、持ってみるととにかくド迫力なんです。それがBWCのダブルキャップカートでドカドカ動くなんて、想像しただけでドキドキします。
今年の11月にはサラ・コナー役のリンダ・ハミルトンも出演する新作『ターミネーター:ニュー・フェイト』も公開される“ターミネーターイヤー”ですのでピッタリ。
価格は約17万円との事。
そしてもう1挺注目なのは、新しく起ち上がったメーカー、イナーシャセンス製
コンバットコマンダーです。
GM-7/7.5をベースに作られる、こだわりのコマンダーとの事。
コマンダー好きにとってはまさに待望の正調コマンダー、これは楽しみです。
こちらのサイトを見ると、GM-7.5を活かしながら細部にまで拘って作られているのが分かります。色も美しい(写真では正確には分かりませんが)。
コマンダーは5インチガバのスライド前方を切り詰めただけではできません。
特に難しいのは、スライドのアゴを後ろに延長するのと、スライドストップノッチ、分解用切り欠きの位置を変更しなければならない点です。5インチスライドを加工してこれを実現するためには、「継ぎ」や「埋め」を行う必要があり、発火仕様ではその部分の強度が問題となるはずです。イナーシャセンスがそのあたりをどのように解決しているのか注目です。
価格はアームズマガジンによると約7万円との事。
今後のイナーシャセンスの動きにも期待しています。
長いガバと短いガバ、気になる製品が立て続けに発表されて、財布が心配になっています。
どちも個人的に注目の製品です。
まずはおなじみ、BWCから、
ハードボーラーです。

(画像はMGC製)
いわゆるターミネーターの銃です。
これまでGM-7で6インチモデルはカスタム製品として発売された事がありますが、7インチモデルは初めてです(たぶん)。
スライドは新規金型で製作され、ワイドトリガーなどの特徴的なパーツもロストワックスや削り出しで作られるとの事。
7インチガバって、持ってみるととにかくド迫力なんです。それがBWCのダブルキャップカートでドカドカ動くなんて、想像しただけでドキドキします。
今年の11月にはサラ・コナー役のリンダ・ハミルトンも出演する新作『ターミネーター:ニュー・フェイト』も公開される“ターミネーターイヤー”ですのでピッタリ。
価格は約17万円との事。
そしてもう1挺注目なのは、新しく起ち上がったメーカー、イナーシャセンス製
コンバットコマンダーです。
GM-7/7.5をベースに作られる、こだわりのコマンダーとの事。
コマンダー好きにとってはまさに待望の正調コマンダー、これは楽しみです。
こちらのサイトを見ると、GM-7.5を活かしながら細部にまで拘って作られているのが分かります。色も美しい(写真では正確には分かりませんが)。
コマンダーは5インチガバのスライド前方を切り詰めただけではできません。
特に難しいのは、スライドのアゴを後ろに延長するのと、スライドストップノッチ、分解用切り欠きの位置を変更しなければならない点です。5インチスライドを加工してこれを実現するためには、「継ぎ」や「埋め」を行う必要があり、発火仕様ではその部分の強度が問題となるはずです。イナーシャセンスがそのあたりをどのように解決しているのか注目です。
価格はアームズマガジンによると約7万円との事。
今後のイナーシャセンスの動きにも期待しています。
長いガバと短いガバ、気になる製品が立て続けに発表されて、財布が心配になっています。
2019年08月20日
動画:SIG P226EVO2発火

先日の記事で予告した通り、SIG P226R EVO2の発火動画をアップしました。
発売から1ヶ月経っており、すでに発火動画をアップされている方がいますので、自分は3マガジン、計45発を撃ち切るところを1カットで撮る事にしました。
個体によっては箱出し快調の物もあるようで、そういうのを入手された方から見ればこれぐらいの作動は朝飯前かも知れませんが、自分の購入した個体はなかなか1マガジンをノートラブルで撃ち切る事ができず、前回の記事にある通りあちこち調整したので、万感の45連射です(笑)。
ともあれ、さほど難しい調整ではありませんし、一度調子が出ればこの製品のポテンシャルの高さが発揮されます。
300発発火した今もバレル、スライドなど破損の気配なし。
超ド級の発火マシーンになり得る製品です。
アーリーモデルやP220シリーズも順次EVO2化していくものと思われますので、これからの展開も楽しみです。
2019年08月18日
SIG P226 EVO2発火調整

発売から1ヶ月が経ったSIG P226 EVO2、箱出しでは細かい作動不良があって1マグ完射できない事も多かったのですが、調整をした事で現在ではほぼノートラブルで発火できるようになりました。
以下に実施した調整を記しておきます。
●不発
従来モデルでは不発はほとんど起きなかったので、少々面食らいました。
モデルガンパーツショップM9の店長ブログでも指摘されている通り、トリガーを一気に引き切る(ガク引き)と、不発が起きにくい事が分かります。
この事からAFPBが解除されにくいのが不発の原因だと推測できるのですが、SIGのスライドは分解ができない事になっていて、Fピンロックを加工する事は難しいです。
そこで同ブログで解説されている通り、ガク引きを繰り返してFピンとFピンロックとの接点の当たりを取る解決策があると思います。
自分の場合にはもう少し手っ取り早い方法にしました。
Fピンロックを下からほんの少しだけ押した状態で、Fピンを後方から押し込んで前進させます。

ロックに阻まれてFピンが止まってしまうようなら、さらにFピンロックを少し押します。
ある時点でロックが解除されてFピンが前進するはずですが、ポイントは「Fピンが前進するけど、ロックの抵抗を感じる」というギリギリのところでFピンを前後に往復させる事です。100回もやればFピンとロックの接点は削れると思います。
これでロックの解除は早くなり、不発は減ると思われます。
●スライドストップがかかる
最終弾でないのに、スライドストップがかかってしまうというトラブルが頻発しました。
EVO2カートはパワーが強い上に軽いので、発火の衝撃でマガジン内のカートが暴れて、スライドストップに接触しているのではないかと思います。
そのためか、弾頭部分と接触しそうな箇所はすでに斜めに削られており、メーカー側でもある程度の対策はされているようです。

しかし、これでは不十分でしたので、さらにスライドストップの、マガジンフォロアーがかかる箇所を削って短くしました。
あまり削りすぎると、今度はマガジンフォロアーをなめてしまい、最終弾発火後にもスライドストップがかからなくなってしまうので注意が必要です。
自分の場合には、赤線の長さをノギスで測った時に、6ミリ弱になるまで削りました。

※長さはスライドストップ外側から、マガジンフォロアにかかる先端までの参考値です。
●送弾不良/閉鎖不良
フィーディングトラブルが多発しましたが、これはいくつかの原因が複合していると思います。
○フィードランプを削る

写真はストーブパイプジャムが起きた時のものですが、発火したカートは問題なく排莢され、チャンバーへ送り込まれるべき次弾が写真のように飛び出している状態です。
これはマガジンリップを広げて少し角度をつければ解消しそうな気もしますが、予備マガジンをすべて同じようにしなければいけなくなるので、自分の場合にはシャーシと接するフィードランプの端を削り、なるべくシームレスになるようにしました。

ここの段差に弾頭が当たる事によって、軽量なEV02カートが跳ね上げられたのだと思います。
○フィードランプをさらに削る/デトネーター先端を削る

チャンバーに送り込まれる途中で止まってしまっている状態です。
これはフィードランプをさらに奥まで削って角度をなだらかにする、

デトネーター先端を削って、カートが斜めに入って来てもひっかからないようにする、

などの対策をしました。
○ブリーチフェイス/エキストラクター加工

チャンバーにはきちんと送り込まれているのに、スライドが閉鎖していません。
これはエキストラクターがカートのリムをうまく咥えられていない状態です。
以前、アーリーモデルの調整方法として、ブリーチフェイスのカートを保持するラグとエキストラクターを削って、スムースにエキストと噛み合うようにする方法を書いてました。今回も同じ方法でいけると思います。
レイルドモデルはエキストラクターを取り外せるので加工が楽です。

カートの下側を保持する段差部分は、今回は結構大胆に角を落としました。
ここは最終弾まで確実に保持するための形状と思われますが、ガバやグロック、USP等にはないわけですから、多少削ってしまっても問題ないと思います。
以上が当方の調整したポイントです。
試行錯誤しながらだったのでこれだけの調整量になりましたが、実際にはこれらすべてを行わなくても快調作動へ持って行けるかも知れません。
近く発火動画もアップしようと思います。
2019年08月15日
無刻印ステンレスマガジン

先日開催されたブラックホールのタニオ・コバブースで、7連ステンレスマガジン【ベース刻印ナシ】というのが販売されていたので、2本購入しました。
新発売ですよね?コレ…
告知も話題もなくひっそりと発売されましたが、実は地味に嬉しいです。
錆びにくいステンレスマガジンというのは発火派にとって頼もしいアイテムですが、タニコバ製の7連ステンレスはコルト刻印のみ発売されていました。
コルト刻印だとスプリングフィールドだのキンバーに使用するのにやや抵抗があります。
もちろん使用に問題はありませんが、コーディネートセンスとしてどうかと思うのです。キンバーにコルトのグリップはつけないでしょ。それと同じです(笑)。

ベース無刻印なら、どんなガバにも合わせられます。
錆びにくく性能抜群、そして汎用性が高い、超重宝しそうなマガジンです。
2019年08月06日
ベレッタのスライドストップ浮き対策
マルシン製ベレッタ92FSの持病として、使用しているうちにスライドストップが外側に浮いて来るというものがあります。
マルシンベレッタを持っていれば、多くの人が経験する「あるある」です。
前回のマルシンベレッタ記事のコメントで、この件に関する質問がありました。歴史ある持病なので、対策法を知る人も多いと思いますが、そういえば当ブログでは一度も言及した事がなかったので書いておきたいと思います。秋以降に再販もある事ですしね。
マルシンベレッタのスライドストップが浮き上がると、最終弾発火後にマガジンフォロアーがスライドストップを乗り越えてしまいます。そうするとマガジンを抜く事もできなくなる非常に嫌な現象です。マルシンベレッタのオーナーであれば、ぜひ対策しておきたいです。
最もメジャーな方法は、グリップパネルの裏側にプラ板などを貼りつける方法です。

赤矢印の部分に、1mm程度のプラ板を貼りつけます。
もちろん、プラ板じゃなくても、金属板でも何でもイイでしょうし、パテなどを盛っても良いでしょう。
自分の場合には、プラリペアを盛っています。

見えない箇所なので適当に盛っていますが、厚さは1mmで、ヤスリで平らにならしてあります。
また青矢印の箇所にある突起は、ある時期からメーカー側で対策のために設けたもののようです。
この突起でフレームを押さえつけ、そのフレームでスライドストップを押さえつける作戦っぽいです。
自分のグリップは突起があるタイプで、そこへプラ盛りもしているので、しばらくスライドストップ浮きには悩まされていません。
このようにメーカー側で改良されていたりしますが、マルシンベレッタはロングラン商品なので中古で入手する機会もあるでしょうし、実物グリップに交換される方も多いでしょうから、新しいグリップに対策されているから大丈夫とも言えませんね。
金型の古さからスライドストップ軸の通る穴の位置がおかしくなっているという話もネットで見た事があり、その場合にはスライドストップ軸を太くして対策するらしいのですが、機会があればその方法も試してみたいと思います。
マルシンベレッタを持っていれば、多くの人が経験する「あるある」です。
前回のマルシンベレッタ記事のコメントで、この件に関する質問がありました。歴史ある持病なので、対策法を知る人も多いと思いますが、そういえば当ブログでは一度も言及した事がなかったので書いておきたいと思います。秋以降に再販もある事ですしね。
マルシンベレッタのスライドストップが浮き上がると、最終弾発火後にマガジンフォロアーがスライドストップを乗り越えてしまいます。そうするとマガジンを抜く事もできなくなる非常に嫌な現象です。マルシンベレッタのオーナーであれば、ぜひ対策しておきたいです。
最もメジャーな方法は、グリップパネルの裏側にプラ板などを貼りつける方法です。

赤矢印の部分に、1mm程度のプラ板を貼りつけます。
もちろん、プラ板じゃなくても、金属板でも何でもイイでしょうし、パテなどを盛っても良いでしょう。
自分の場合には、プラリペアを盛っています。

見えない箇所なので適当に盛っていますが、厚さは1mmで、ヤスリで平らにならしてあります。
また青矢印の箇所にある突起は、ある時期からメーカー側で対策のために設けたもののようです。
この突起でフレームを押さえつけ、そのフレームでスライドストップを押さえつける作戦っぽいです。
自分のグリップは突起があるタイプで、そこへプラ盛りもしているので、しばらくスライドストップ浮きには悩まされていません。
このようにメーカー側で改良されていたりしますが、マルシンベレッタはロングラン商品なので中古で入手する機会もあるでしょうし、実物グリップに交換される方も多いでしょうから、新しいグリップに対策されているから大丈夫とも言えませんね。
金型の古さからスライドストップ軸の通る穴の位置がおかしくなっているという話もネットで見た事があり、その場合にはスライドストップ軸を太くして対策するらしいのですが、機会があればその方法も試してみたいと思います。